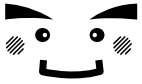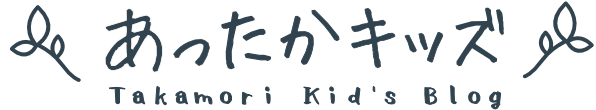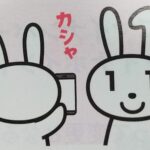★はじめ
夏の風物詩の一つ《七夕》
現在は新暦7月7日に祝う地域が多くなりましたが、旧暦(農暦)にあたる8月下旬(2025年は8月29日)に祝う地域もまだ残っています。梅雨が明け夏の星空が特に美しい時期。天体に詳しくない私でも、天の川を見つけられる。
子どもたちは、伝統行事として《七夕》を教えてもらいお祝いしているだろうな~。公共の施設でも短冊をつるした七夕飾りを目にするが、家庭ではどうなのかな?
子どもの頃は、笹の枝に短冊をつるし、希望や願いごとが叶いますようにと星空を見上げた思い出が…。今は忙しさに紛れ、もう何年も《七夕》を特別意識して祝う、星空を見上げる余裕を失くしてる。
◆《七夕》の由来・起源

《七夕》は、一年の重要な節句をあらわす五節句の一つと数えられ、毎年(旧暦)7月7日の夜、願い事を書いた色とりどりの短冊や飾りを笹の枝につるして、星にお祈りする行事。
※五節句:人日(1月7日)、上巳(3月3日)、端午(5月5日)、七夕(7月7日)、重陽(9月9日)
中国の織女と牽牛(織姫と彦星)の二つの星が天の川を越えて年に一度の逢瀬が叶うその夜に、織物上手な織女/織姫にあやかって機織りや裁縫、後には歌や音楽など諸々の技芸上達を祈る「乞巧奠(きっこうでん)」行事が、奈良時代ごろ日本に伝わり、古来の「棚機(たなばた)」がまじりあった行事が起源と言われ、江戸時代には幕府により公式な祝日とされ、宮中行事や習慣が庶民の間で広まり、少しずつ今の七夕に…。
◆変化し続ける《七夕》

伝統的な行事とて《七夕》を祝うとともに、今は自分らしく家族や恋人と楽しむ行事としての一面もあるように…。中国ではロマンチックな「織女と牽牛(織姫と彦星)」伝説から、《七夕節》=『夏のバレンタインディー』恋人と楽しむ日が定着してきています。それは日本も同じで《七夕》イベントの主なターゲット層は、家族と恋人が多い。
《七夕》の食べ物は、五色のそうめんや伝統的な菓子がありますが、今は和菓子・洋菓子ともに暑さを和らげてくれる、涼しげな色の天の川やロマンチックな伝説を取り入れた創造菓子が多くなってきています。(様々な菓子は、職人たちの腕の見せどころにもなっていそう)
★まとめ

大小のストレス、予期せぬこと悪いうわさも飛び交い、今は様々な理由で忙しく心に余裕がない人が増えているように思う。ご多分に漏れずこの私もその一人だ。今年も特別なことが出来ずに当日を迎えてしまった。(もし何枚もの短冊に願いごとをあれこれと書いたら、多すぎて笹の枝が折れてしまいそうw)
《七夕》の7月7日頃は梅雨の時期と重なり、祝い気分や綺麗な星空が眺められない時も…。今年は最速で梅雨明けし、例年よりも早くから綺麗な夏の星空を楽しめる機会が増えそう。
暑さしのぎも兼ね、庭先やベランダに出て家族や恋人とお喋りしながら、嫌なことを忘れ夏の星空を見上げてみようか…。天の川と織姫星(ベガ)と彦星(アルタイル)を探し「二人は出会えたかな?」と想像してみるのも。
近くにプラネタリウムがあれば、夏の星空をテーマにしたプログラム『七夕・夏の夜空』を楽しむ。家庭でもプロジェクターで夏の星空を映し、ゆったりと七夕の夜を過ごしてみるのも…。